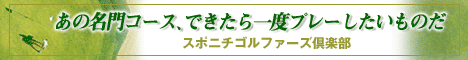
|
|
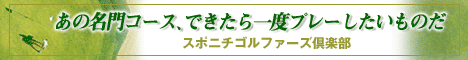 | ||||
|
| |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
|
西表でマングローブ倒木被害 「大量・駆け足」観光原因
日本最大のマングローブ林が広がる西表島で、深刻なマングローブの倒木被害が起きている。大量の観光客をさばくために遊覧船が速度を上げ、その波が根元を浸食するのだ。同島では自然への影響を最小限に抑えようと、小人数での「エコツーリズム」を全国に先駆けて始めたが、この試みも、理想と現実とのギャップに直面している。【元村有希子】 ◆遊覧船の波受け
「タコの足のようなヤエヤマヒルギの支柱根は、稚魚を外敵から守ります。潮が引けばカニやエビが出てきますよ」。案内してくれた蒲田愛美(めみ)さんは石川県出身。西表島の自然にほれこみ、移り住んで14年になる。 「異変」を目にしたのは、河口から1キロほどさかのぼった辺りだ。川幅の広くなったところで、右岸のマングローブが約50メートルにわたって倒れていた。根元の土がえぐれ、自らを支えきれなくなったのだ。「遊覧船の引き波が原因。潮の干満では、こうはなりません」と蒲田さんは話した。 ◆観光客が急増 沖縄本島から南西へ約400キロ、人口1900人の西表島に昨年度は29万人の観光客が訪れた。10年で2・4倍に増えた。だが大半は隣の石垣島からの日帰り。港で遊覧船に乗り換え、マングローブ林を見ながら仲間川を上る。その航跡に立つ波が「マングローブに悪影響を及ぼす」という声が出始めたのは、ここ数年のことだ。 環境庁(現環境省)は99年末〜00年3月に、仲間川のマングローブ林被害を調べた。その結果、川幅の広い直線部分が、最高40センチ以上の波を1日15〜35回受けていた。調査報告は、船の大型化とスピードアップが原因と指摘し、「自然にふれあうには、ゆとりある利用が望まれる」と提言した。 ◆理想と現実と こうした“駆け足”の大人数観光の弊害をなくそうと、「エコツーリズム」が考え出された。「エコロジー(生態系)」と「ツーリズム(観光事業)」を組み合わせた造語。土地固有の自然や文化を守りつつ、旅行者は感動を、地元は経済的利益を受ける――のが狙いだ。西表島では96年、環境庁の支援を受けて全国初のエコツーリズム協会が発足した。カヌーガイド、釣り、ダイビング業者や旅館経営者が加入する。 しかし同協会の活動は曲がり角を迎えている。「狭い川にカヌーがあふれる。処理施設もないのに、ペットボトルや使い捨て容器の弁当を用意する。客はごみだけ残して日帰り。これがエコツーリズムかい?」。協会を脱会し、自然体験ガイド業を営む村田行(すすむ)さん(51)の指摘は厳しい。 仲間川の遊覧船運航や観光バスを手がける西表島交通は、島で従業員135人前後を雇い、観光収入をもたらす優良企業でもある。「小人数ツアーで経済活性化」というエコツーリズムの理想の実現は容易ではない。 ◆「共存」へ模索 「お客さんの希望と、もうけ主義で、環境を壊してしまった。我々の仕事は自然あってのもの。観光のあり方を真剣に考えている」。批判を受け、同社の玉盛雅治副社長はそう述べた。同社は12隻の遊覧船を、波の立ちにくい新型に順次交換している。また、現在は平均50分間の遊覧時間を、減速により20分間延長することも検討している。 一方、エコツーリズム協会は、ツアー客の人数を制限したり、自然への配慮を明文化した指針づくりを検討中だ。実現のためには会員の合意が大前提となる。だが、「エコツーリズム」についての各会員の考え方はバラバラなのが実情だ。事務局の永井伸子さん(28)は「釣った魚をリリースして自然に返すべきかどうか、といったことだけでも人々の意見は分かれる」と指針づくりが難航していることを認める。 自然を愛する気持ちは誰も同じ。保全と利用のさじ加減をめぐって模索が続く。
|
|
|
|
|
| Home | 毎日の視点 | くらし・娯楽 | 子育て・教育 | ウーマン | スポーツ・芸能 | DIGITALトゥデイ | |
|
|
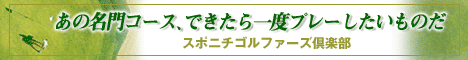 |
|
|
Copyright 2001-2002 THE MAINICHI NEWSPAPERS.All rights reserved. 毎日インタラクティブに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。 著作権は毎日新聞社またはその情報提供者に属します。 |