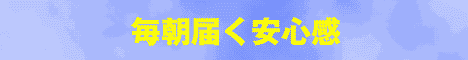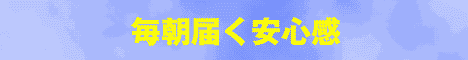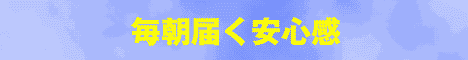|
|
マングローブ林、生態系の“揺りかご”
 |
| 根元の土がえぐられ、倒れたマングローブ=7月17日、西表島の仲間川で
| 国際マングローブ生態系協会事務局長の馬場繁幸・琉球大助教授(造林学)によると、マングローブ林は、長い間、「無駄な土地」として埋め立てられたり、燃料用に伐採されてきた。近年の研究で生態系の多様さや、海を汚染から守る働きが分かった。
日本のマングローブ林は500〜600ヘクタール。沖縄は面積・種類で圧倒的な比重を占める。「植生だけでなく、底にすむカニや貝、それを食べる鳥、林に暮らすイリオモテヤマネコなども含めた生態系がとても貴重」と言う。
生態系を変えかねない道路改修や、観光客が林に入って根元が傷むなどの被害を心配する馬場さんは「林に木道を造れば船の便数を減らせる。エコツーリズム・ガイドを地元で養成すれば、自然を守りながら雇用と経済効果も生まれる」と話している。
◇マングローブ
真水と海水が入り交じる「汽水域」に生える植物の総称。膝根(しっこん)、支柱根などの特徴的な根を張る。日本では、オヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギなど7種類が生育し、西表島ではすべてを見ることができる。島の代表的なマングローブ林は島東部の仲間川と、西部の浦内川にある。
(毎日新聞2001年8月12日東京朝刊から) |
|
 |
地域から地球へ〜環境面〜 |
|